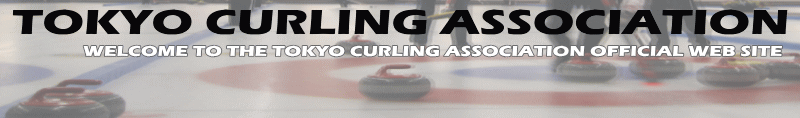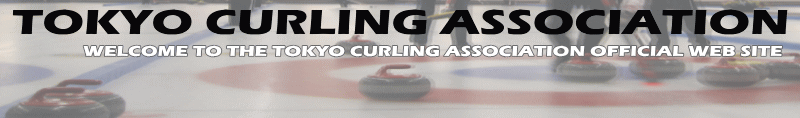|
前回(その7 ラストロック)のクイズ、その考え方と適用の仕方小川 豊和
クイズのシチュエーションは、「ラストエンド、先攻で4-2と2点リードしていて、セカンドの2投目。図のように、相手のコーナーガード(白のストーン)がハウス前左側にあって、自分たちのストーンがハウス右側、4フット円にかかっている。けれどもこのストーンはオープン(相手がいつでもテイクアウトできる)。」です。次のショットとしては、いろいろなオプションが考えられます。しかしその中でも、与えられた条件下でまあ妥当であろうと考えることができるオプションは、以下の4つと考えられます(作戦のヒント:一度に最もふさわしい答えを見つけようとしない。××コンテストでも、予選を行ってまず何人かを選ぶでしょ!それからどれが一番いいか考えればいいんです)
1. 黒のストーンをガードする。
2. 相手のコーナーガードの後ろ、ハウスの反対側にドローする。
3. コーナーガードをはずす。
4. ハウスの頭、12フットにかかるが、相手がヒットしてもハウスにはかからない位置にドローする。 |
|
ここで、シチュエーションをもう少し注意深く見てみましょう。
「ラストエンド、先攻で4-2と2点リードしていて、…」
このエンドを終わった時点でリードしていれば勝ちだ!
「ラストエンド、先攻で4-2と2点リードしていて、…」
ハウスの中心に向かってプレーする。ということは、相手はハウスのサイドに向かってプレーしたいわけだ。これを邪魔する方法は…
「ラストエンド、先攻で4-2と2点リードしていて、…」
リードしているので(もう点数はいらない!)、ディフェンスを中心としたプレーを選ぶ。ということは、ヒットがいい(ストーンの数を減らす方向)。
「…セカンドの2投目。図のように…」
フリーガードゾーンルールは気にしなくていいんだ。 |
|
こういう風に考えると、
1.
ストーンの数を増やす方向にある。また、守りたい気持ちはわかるが(欲張りだねえ)、相手にハウス内の黒のストーンにフリーズを決められたり、反対側へドローを決められて、3点取られる危険性が残る
(20点) 。
2.
相手はこのエンド2点取らないと負けてしまうので、相手にプレッシャーをかけようという気持ちはわかる。ショットが決まればいいが、決まらないと1.と同じように相手に3点取るチャンスを残してしまう。また、相手にプレッシャーをかけるのであれば、こちらが苦しい思いをしてドローを決めるより、もっと簡単な方法があるんじゃ…(40点)。
3.
いいセンスしてますねえ。まだセカンドのショットだからと言わず、将来問題となる可能性のあるものは、未然にその芽をつんでおきましょう(100点)。
4.
センターを占領して、相手のスキップにプレッシャーをかけると言う気持ちはよく分かります。でもこの状況では、もう得点は必要ないのですから、あまりハウス前にストーンをためると、相手がロールするのに使ったり、タップバックで、後ろに壁を作られたりと、ハウス内のストーンの数が増えてきそうな気がします。もっと簡単にいこうよ(50点)。ということになります。
もう一度まとめておきます。FESRAINの7つの要素については、上のクイズでは、EとSとRを他の要素より重んじて考えています(下の表参照)。 |
|
F
|
E
|
S
|
R
|
A
|
I
|
N
|
|
フリーガードゾーンルール
|
エンド
|
スコア
|
ロック
|
アビリティー
|
アイス
|
残りのストーン
|
|
×
|
○
|
○
|
○
|
×
|
×
|
×
|
また一般に、
・ 先攻の場合はハウスのセンターに向かってプレーをする(相手はハウスのサイドに向かってプレーをするので、これを何としても阻止する!)
・リードしているときは、ヒットを中心としたディフェンス(ストーンの数を減らす方向)の組み立てをする。ドローはハウスの中へ入れ、相手に打たせる(ストーンの数を減らす方向)。
・ 負けていればオフェンスを心がける(ストーンの数が増える方向)。従って、ドローはハウスの中にいれず、まずハウスの前に止める。相手のストーンがハウス内にあっても、あえて取り出さず、フリーズとか、タップバックとか、ストーンをためる試合を目差す。
などの作戦は、ほぼ全てのシチュエーションに適用できると思います。
初心者の方は、自分たちの技量に応じた(上のFESRAINではA)作戦をまず心がけてください。ヒットが苦手であるのに、セオリーではヒットだから、絶対ヒットでないといけないということはありません。強く投げようとしてバランスを崩し、ストーンを無駄にするのであれば、投げやすいショットを選びましょう。まず、たくさん試合に参加して、いろんなことを経験してください。慣れてきたら少しずつ難しいショット、難しい場面での作戦を考えていけばいい、それくらいの気楽な気持ちで!!
|